 |
 の話 の話 |
| 借家と家賃 | 土建屋さん | 浴槽がない! |
| 赤瓦 | 八重山の墓 | ステータスシンボル |
| 海が見える家 | 幻の住民 | シーサー |
| 不動産バブル | 香り豊かな | 離島に住む無念 |
| 暮らしの香り |
 |
 の話 の話 |
| 借家と家賃 | 土建屋さん | 浴槽がない! |
| 赤瓦 | 八重山の墓 | ステータスシンボル |
| 海が見える家 | 幻の住民 | シーサー |
| 不動産バブル | 香り豊かな | 離島に住む無念 |
| 暮らしの香り |
【借家と家賃】
石垣島は、たった人口48,000人ほどの小さな街なのに、
アパートや借家がヤケに多いし、今でもアパートや借家はバブル期なみの建築ラッシュなのだ。
八重山の共同住宅の建築確認件数は、平成22年度頃には1年平均7〜8軒だったのに、
平成28年には1年に40軒を超え、
観光客や移住者の増加による人口増を当て込んで、今後、さらに増えそうな気配を見せていて、
いっこうに建築ラッシュが止まる気配がないのだ。

しかし、
これは何も内地人(ないちゃー)の移住者用の需要だけではない。
沖縄、ことに八重山地方は多産で、子供は平均4〜5人。
17〜8歳でお母さんになるという人も多い。
この子供たちが成人して分家すると・・・・・・
アパートや借家が、いっぱい要るのです。
しかも、沖縄では昔から長男の実権がつよく、
親が亡くなったとき、親の財産のほとんどは長男だけが相続してしまいます。
相続する家のない次男や三男たちは、追い出されてみんな借家を借りるのです。
そんなわけでアパートや借家は大流行、
この島には不動産バブルの崩壊の影響はありません。
そのせいかどうかは知らないが、
なぜかこの島の家賃はムチャクチャ高いのです。
1DKで40,000円〜50,000円はザラ
2DKなら65,000円〜70,000円
築後40年くらい経った雨漏りする一軒家でさえ、
70,000円くらい、
オシャレな30坪くらいの家なら
150,000円くらいするのです。
おーこわ!
| 借家は不動産屋を通さずに足で探す これ、島の知恵 |
【土建屋さん】
八重山には土建屋(土木建築業者)さんがとても多い。
たった50,000人(八重山地域全体の総人口)の地域に、
実に600社を越える土建屋さんがあるのです。
なんで、こんなに土建屋さんが多いのかと言うと・・・
この南の島には、元々これと言った産業がなく、
サトウキビ栽培と牧畜(ヤギ)と漁師(漁業)と、
要するに、
自給自足して現金収入を得るための細々とした産業しかなかったのです。
このため、
戦後、アメリカに占領されていた沖縄は、
昭和47年(1972)5月15日に日本領に復帰し、
この30年強の間に少しずつ内地との経済格差が少なくはなったが、
今でも、内地と沖縄との所得格差はとても大きいのです。
本土との経済格差を表現する際によく使われるのが、1人当たりの県民所得。
平成15年の統計によると、
全国平均271万円に対して沖縄は204万円で、もちろん日本一低く、
全国最高の東京の1人当たりの県民所得、426万円の半分以下の水準なのだ。
平均失業率は7.8%、これも日本最低だ。
そのため、「沖縄離島振興法」という地域立法で、
港湾や道路、学校や公園など。莫大な整備予算が沖縄に投入され、
この30年近く大規模な土木建築工事が沖縄じゅうで行われたのです。
産業の少ないこの地域で、八重山人(やいまんちゅー)はみな、
道路工事の人夫仕事なんかで現金収入を得て、なんとか暮らしてきたので、
とても土建屋さんが多いのです。
公共工事がないと、八重山人は、とてもマトモには食っていけないのです。
それにしても、
50,000人の狭い地域に実に600社の土建屋さんというと、
600社×30人(社員・下請・家族の数)=18,000人ということなので、
なんと人口の3割以上が土建屋さんというものスゴイ計算になるので・・・
それだけ土建屋さんが居れば、
「土建屋政治」と非難されるわが国の政治の世界の慣例では、
数の論理で、新石垣島空港なんかはゼッタイに実現するだろうし、
八重山の「住」は、何の心配もないはずなのです。
ところが、右を向いても左を見ても、土建屋さんだらけで、
猫も杓子も自称「土建屋さん」なので、
中には、プロなのかアマチュアなのか分からないようないい加減なのが多く、
僕は、自分の家の大工仕事や水道・電気仕事を、「プロ」に任せることができず、
ぜ〜んぶ自分でやるのです。
 |
これは昔の本物のプロの技 「貫屋」という釘を使わない工法だ |
|---|
| 赤瓦の雨漏りを直すのはとても難しく、 メタボの僕が屋根に乗ると余計に壊れる |


| それでもやっぱり本物の温泉は恋しい! 誰か掘らないかね? |
【赤瓦】

沖縄の赤瓦はとてもカッコウがいい
赤瓦の沖縄木造家屋に住んでいると、
なんだか昔から沖縄人(うちな−)だったようで、
なかなか居心地がいいのです。
沖縄の赤瓦は、昔からずっと沖縄のものであったように思われているが、
実は、その歴史は以外と新しく、18世紀以降のものがほとんどで、
首里城の発掘現場などからは、赤瓦だけでなく、
それより古い時代の、内地と同じように上薬をかけて焼いた灰色の瓦も出土する。
なぜ、沖縄で18世紀以降、赤瓦が主流となったのかと言うと、
18世紀に社寺や城郭・役所などの建設が盛んになり瓦需要が高まったので、
燃料となる薪の量が少なくて済み、技術的にも簡単な素焼き赤瓦の生産が広がり、
コスト面が重視されて沖縄じゅうに素焼きの赤瓦が広がったのだ。
この赤瓦は、男瓦(ウーガーラ)と女瓦(ミーガーラ)で構成されていて、
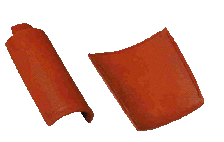 |
| 男瓦(ウーガーラ) 女瓦(ミーガーラ) |
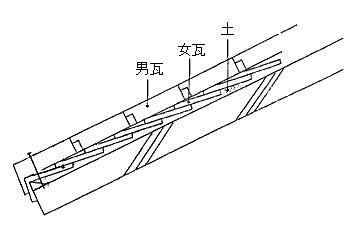

 |
※沖縄では、石垣島の「於茂登岳(おもとだけ)」の8合目より上部に自生している女竹が「虫が付いてない」ので珍重され、首里(那覇)にも船で送られた |
| そして、去年の台風時にも、 我が家のパソコンを濡らしてパーにしたので、その買い替えで、またまた懐が寂しいのです |
【八重山の墓】

「住」とは言えないが、墓の話。
内地では、墓地というものは海の見える丘の上や、
お寺の境内にあるものだとみんな思っているが、
もともと仏教国でなかったこの島には「寺院墓地」というものがなく、
この島の墓地は、家の周りや街中にあるのが普通だ。
| 八重山には、もともと寺などなかったが、薩摩藩の進言に よって寺がないのもどうかと言うことで、1614年に桃林寺 という寺が建てられたのです。 日本最南端の仏教寺院:桃林寺  |
家の周りに墓地があるのは、かつては沖縄には集団墓地が無く、
個人の敷地の中にお墓を作っていたためなのだ。
この島はなにしろ離島なので、今でもだいたい墓は何処に建ててもいいのだ。
大きな亀甲墓(きっこうばか)には、庭や屏風(びんふー)なんかもあって、
まるで「家」のようだ。
与那国島の祖納集落の程近く海岸沿いにある浦野墓地群の風景は
まるで異国のようだ。
墓の規模も八重山諸島の中でもずば抜けてデカイ。
「遺跡」と呼べるほどの大きさで、大型のものは家一軒ほどの大きさなのだ。
 これが屏風(びんふー)/矢印 ※宮良殿内(みやらどぅんち) |
 |
| 八重山の「十六日祭」 旧暦の1月16日、一般にこの日をグソー(後生、あの世、他界)の正月とする観念があり、墓に詣でたり仏壇にお供えをして祖先をなぐさめる日である。 こんな行事は、祖先を供養するものとしてはほぼ琉球列島全域に名前を変えて分布している。 |
そう言えば、沖縄映画の名作「ナビィの恋」のデートの場所も墓場だったな。
 |
映画「ナビィの恋」から |
| 100年前までの八重山は「風葬」だった。 つい何年か前まで、風葬の無縁ガイコツが道路の横にゴロゴロと安置されていたりもしたが、2005年に宮古島からやってきた怪しげな「ユタ」の集団が、「津波を防ぐオマジナイ」と称して石垣島の風葬場所をいっせいにコンクリートプロックで覆ってしまったので、今ではそんな場所は石垣島には無くなったが、離島には、まだまだそんな場所が残っているのだ。 |

| アパートの家賃の滞納は多く、2年近く払ったことのないという強者も居るのだ |

| 「海が見える」だけで地価が倍に跳ね上がる |
|
|
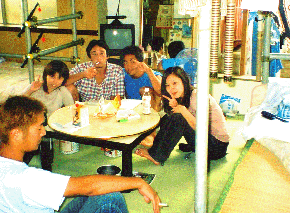
| キャンプ場に住んで、そこから仕事に出かける若者なんかも大勢いるのだ |
|
【シーサー】 赤瓦の上に鎮座して家を魔物から守る。 今ではすっかり「沖縄の顔」になったシーサーだが 実は意外と「新顔」なのだ。 もともとは瓦職人達が瓦を葺き終わった際に 余った瓦や漆喰などで作って「これを魔除けにするといいさー」 てな感じで施主にプレゼントしたのが始まりと言われている。 いわば、瓦職人の遊び心。 正式な魔除けとして古くから親しまれてきたものではないのだ。 島のオジィに言わせれば、 実際に八重山で見られるようになったのは、沖縄が日本に復帰した昭和47年前後からで、 竹富島の民家から流行り始めたようだ。 正式な魔除けではないので 格式のある家などでは乗ってない場合が多いのだ。 いわゆる「原型」なんてものも存在しないわけだから 今ではピースをしたり、逆立ちしたり、いろんな「子供達」が次から次へと生まれている。 もちろん、今も昔も専門の「シーサー職人」なんてものは存在しなかったのだ。  この島では、近年、赤瓦の木造家屋がめっきり減った。 昔ながらの建築方法で赤瓦の家屋を建てると、建築費が鉄筋コンクリートの倍もする。 家を建て替える際には当然お金を借りるわけなのだが、 融資先の銀行などでは、一時期「赤瓦は贅沢」という風潮があり、お金を貸し渋ったために、 結果として、鉄筋コンクリートの家屋が増えたわけで、何も台風対策だけではないのだ。 その際、よく目立つ屋根の上のシーサーも「贅沢」とされ、 シーサー君は、しぶしぶ屋根を下り、 ひっそりと玄関の門の上に乗ったのだ。 この様子を、ある島人は、 「昔はマジムン(魔物)から家を守ったけど、今は人間から家を守ってるわけさ、 今は人間の方が魔物より恐ろしいからよー。」 と、ニコニコ顔で話すのである。 うーん・・・言い得て妙である。
【不動産バブル】 新石垣空港が出来た。  前の空港は滑走路が短かく150人乗りの小型ジェット機しか就航できず、 天候に左右されやすく、悪天候時には欠航も多い。 かつての香港空港のように、街中にあってブッソウでもあった。 そんなこんなで、賛否両論30年もスッタモンダした末に、 「新石垣空港」というのが本決まりしたのだ。 (2000m滑走路の新空港では中型ジェット機の就航が可能) 八重山人(やいまんちゅ)の多くは、 新石垣空港が出来れば、 内地の資本やノウハウが入ってきて島が活気を帯びるとか、 農水産物を那覇で積み替えずに直接東京や大阪など消費地に運べるとか、 「離島」が解消されるとか・・・・ いろんな期待をこの空港に賭けているのがよく分かる。 反面、これを見越した宿やマンションの建築ラッシュや、 内地の需要によるミニ不動産バブルが、この南の島を沸き立たせているのだ。 2年前まで坪15,000円でも買手のなかった島の北部の不便な土地が、 最近では坪60,000円だとか・・・ なかには「坪100,000円なら売ってもいいさー」とか、 とんでもない声がアチコチから聞こえてくるようになった。 土地の価格は、土地を活用して得られる経済的利益によって決まる。 東京から2,000kmも離れた日本のいちばん端っこの南の島の、 市街地から40kmも離れた 人口40人の何もない集落の 台風が来れば1週間も停電するような、 そんな経済的利益のないところの土地が、 坪100,000円もする道理がないのだ。 産業が乏しく大金を手にする機会の少ないこの島の人たちの、 それなりの期待はよく分かるのだが・・・・・・・ 土地が高くなれば、自分たちも買えなくなるうえ、 誰かがババを引くことになって辛い思いをするのは、結局は島人(しまんちゅ)自身なのに、 誰もが売ることだけを考えて買うときのことを考えない。 内地の資本は美味しいところを食べればいずれは出て行く。 島から出ない島人には手の出ない不当に高い土地だけが島に残されるのだ。 島の次男や三男の諸君、もう君たちの分家の家作りは無理ですね。 人のこころはあまりにも弱く、 僕はとても悲しい。
【香り豊かな木の住まい】 沖縄の家と言えば、コンクリート。 沖縄にはコンクリートの住宅以外は少ない。 日本(大和)では今も木造が主流、 どうして、日本の家と沖縄の家は違うのだろう・・・ 戦前までは沖縄も木造住宅が主流だったが、 戦後、米軍統治時代の基地内外のコンクリートの米軍施設の影響が、 沖縄の家をコンクリート化したのだ。 また、戦後の時代には、 沖縄中が戦火で焼け野原で、家を建てられるような木なんかはほとんどなかった。 このため、 沖縄の建築文化は、半世紀前に一変したのだ。 もともとの沖縄の家は、もちろん木造で、 ウフヤ(母屋)・一番座(客間)・二番座(仏間)・三番座(居間)・裏座(寝室/台所) と分かれていて、 琉球王朝時代には、 八重山の平民の畳間はすべて6畳以下で茅葺でなくてはならず、 それどころか間取りまでも定められており、 氏族には瓦葺きや、チャーギ(イヌマキ:犬槙)の木の使用が許可されたり、 琉球王朝によってかなり厳格な身分制度がしかれていたのだ。 沖縄でチャーギと呼ぶこの木は、八重山ではキャンギとかケーンギとか呼ばれ、
「堅い」「湿気に強い」「害虫が付かない」ことから、 高温多湿の沖縄で昔から重用されてきた材木で、とても高い。 「キャンギ」とか「ケーンギ」という言葉は、もともと、 (けやけき木)「異木」(きわだった木)というのが語源で、 内地の欅(ケヤキ)と同意で使われる言葉で、 けやけき木(異き木)が訛って「キャンギ」や「ケーンギ」になったのだ。 今では、そんなこともほとんど忘れられ、 この間、宮良殿内で会ったバスガイドは、 連れてきた観光客に、 「この家の木材は高級材の欅(けやき)です。石垣島では欅のことをキャンギと言います。」 と、 かなりいい加減な説明をしていたので、さすがに黙っておれず、 横から口を出して、彼女の面子をつぶしてしまった。 堅くて湿気に強く害虫が付かない木は、このイヌマキ(犬槙)以外にも、 安い外材を探せば他にもあろうと思うのだが・・・、 やっぱり、家は「香り豊かな木の住まい」がいいね。
【離島に住む無念】 八重山は「離島(はなれじま)」だ。 南北40Kmの石垣島の端から端まで走っても 2時間あれば海に突き当たり、そこから先には行けない。 飛行機に乗ればどこにでも行けるが、飛行機はいつでも飛んでいる訳ではなく、料金も高く、 夜中に島外に住んでいる人に会う急用ができても、行きたくても行けない。 これは、実は大変なことで、離島の憂き目を実感させられる。 僕は昔、どうしても行かなければならない用事が出来て、 夜中に四国を出発し、瀬戸大橋を通って、高速道路に乗り、翌朝早くには静岡に着いた。 地続きなら、行こうと思えば行けるのが普通なのだ。 八重山人ほど飛行機に乗る人は他の地域には居ないと思う。 オジィだろうが子供だろうが、 「飛行機に乗ったことがない」という人は八重山にはまず居ない。 こんな離島に住む無念を仕方なく甘受して暮らしてきたが、 新石垣空港の開港後、国内へ就航しているLCC/格安航空会社が次々と石垣島に進出してきた。 最近では、 Peachを例に取ると、石垣−那覇間片道2,280円などと、 これまでの僕の感覚とまったくかけ離れたビックリする格安料金で島外へ行けるようになり、 最近、僕の頭の中から「離島感覚」がすっかり消えうせた。  ほんの数年前まで、石垣島から那覇に行くには、「離島割引」を使っても片道17,000円 往復では34,000円かかったのだ。 Peachの往復4,560円という料金は、これの13%という常識はずれの料金で、 都会でバスに乗るのと同じように気楽に飛行機に乗り 420Km(東京−大阪間とほぼ同じ距離)も離れた那覇に行けるのだ。 これは一体なんなのだろうか? もともとのJALやANAの料金がべらぼうに高かったのか、 はたまたLCC航空の経営努力のおかげなのか・・・・・・本当の理由は僕にはどうにも理解し難い。 およそ経済原則からかけ離れたこの航空運賃の不思議は何処で帳尻が合うのだろう。 @2,280円×200人=456,000円、この程度の収入で ドラム缶500本ものハイオク航空ガソリンを燃やし、クルー6人や整備要員や管理要員の給料を払って 高い空港使用料や事務所の家賃を払い、50億円もする飛行機の減価償却までして、、、、 なんで経営が成り立つのか。 僕の車はリッター5Kmの高燃費車なので、 家から40Km離れた平久保崎まで往復80Km走ると、ガソリン代が3,000円かかる。 ところがPeachは、420Kmも空を飛んで人を運んで2,280円しか取らないのだ。 これを不思議と言わずに世の中に不思議があろうか。 これがアベノミクス効果なのか、経済のグローバル化なのか、デフレの浸透なのか 単なる競争原理の「後は野となれヤケクソ経営」なのか、僕の能力ではもうサッパリ分からん! でも、僕は、ホントはそんな難しい理由はどうでもいいので、ともかくLCC効果を楽しもうと単純に思う。 この料金なら日帰りで那覇へ映画を観に行くことだって出来る。 なんかしらんが、すごいことになったものだね。 ということで、 僕の頭の中では、もう八重山は、「本物の離島」ではなくなり、 一気に“準”離島に格上げになったのです。
【暮らしの香り】 先にも言ったが、 八重山の家のほとんどはコンクリートになった。 でも、 今でも、昔ながらの赤瓦の木造家屋も残っていて、 なぜか、そこに住む人たちは、海人(うみんちゅ)だったり畑人(はるさー)だったりするのだ。  この家の鴨居の上には、賞状だとか亡くなった爺さんの写真だとか、 漁獲の減少から今では海人を辞め陸に上がり、ガイドなどの観光業を営むこの家の主が、 かつてしとめた大物の五色海老の剥製だとかが誇らしげに掛けてあり、 床の間には、 縁起物の掛け軸が掛けてあったり、シキビ(樒)なんかが活けてあったりする。  この家の床の間には、さりげなく三線が飾ってあり、 恵比寿大黒のお面とか、クバ笠とか、三線大会の賞状とかが掛けてあり、 少し古めかしい柱時計なんかが掛けてある。 こんな民家の中の風景は、見慣れた風景のようでもあり、 実は、今の時代では当たり前でなくなった、古き良き時代の風情だと思うし、 こんな八重山の暮らしが、今の日本では、とても貴重なものであることは間違いない。  この家の主は、今でも、昭和30年代のように、こんな竃(かまど)で、ときおり煮炊きをするが、 これは、お客さんが来て、大量に食事を作るときだけのもので、 普段の生活にはガスを使っているのは当然だ。 でも、 クバ笠を被り、地下足袋(じかたび)を履き、脚絆(きゃはん)を巻いてマキを炊く主の後姿からは、 もう八重山あたりにしかなくなっただろう懐かしい「人間の暮らしの香り」がする。 世界のみんなが、こんな暮らしに戻ることができたら、 もう「地球温暖化」なんかは屁の河童で、 人類は、あと2000年くらいは生き残れるかもしれないね。
|