【八重山人(やいまんちゅ−)スタイル】
八重山人の普段着は、男はTシャツと綿ズボンだ。
女はというと、長袖シャツが圧倒的に多く、半袖を着ているのはたいがい内地人(ないちゃー)だ。
海に行くときでも、島人はみんなTシャツ着用だ。
石垣島は日本最南端の島、それだけ赤道に近いので、当然、紫外線の強さは内地の比ではない。
気温があまり高くないからとタカをくくっていては一大事!
あっという間に日焼けしてしまう。紫外線の強さは実に関東地方の7倍だ。
それを知っている島人(しまんちゅ)は、みんなTシャツ着用だ。
海水浴場で島人と観光客を見分けるのはカンタン、
Tシャツを着ないで泳いでいる人が、恐れを知らぬ観光客なのです。
ハワイには「アロハシャツ」というのがあるが、
あのシャツを作ったのが沖縄人だということはあまり知られていない。
沖縄からハワイに移住した人たちが「端切れ」を縫い合わせて機能的なシャツを作り、
それがハワイやカリフォルニアに広まって「アロハシャツ」になり、
日本に逆輸入されたのだ。
この「アロハシャツ」と同じような「かりゆしウェア」というものがあって、
これが、沖縄の礼服や正式な仕事着で、市長だって議員さんだって、
これさえ着ていれば何処に行っても怖いものはないのだ。


石垣市役所のヒトコマ 真ん中の人は前任の市長さん 石垣出身のBEGINもかりゆしウェア
役所の人が着ているのが「かりゆしウェア」、
開襟のカラーシャッで、内地感覚では遊び着にしか見えないが、立派な沖縄の公用着なのだ。
「かりゆしウェア」は夏場の公務員や銀行員の制服に採用されているだけでなく、
葬式のときに着るまっ黒な「かりゆしウェア」もあって、
それはそれで島の風景に溶け込んで少しもおかしくないのだ。
| 「かりゆし(嘉例吉)」というのは「めでたい」という意味だ |
【恐れを知らぬ観光客】
どういうわけか、この島に来る観光客たちは、
国籍不明の異様なスタイルの人が多い。
冬だというのに半ズボンをはいていたり、頭にターバンを巻いている人もいる。
おへそ丸見えの女の子や・・・・・・・
高下駄を履いた女の子、中央アジアあたりの服を着た人もいる。
どこから見ても「乞食」かホームレススタイルの人や
目玉だけが不気味に光る真っ黒に日焼けした破れTシャツの人、
ここは日本最南端のアジアの入口の街なので、国際色が豊かなのだと言えばそれまでだが、
あの格好で内地の繁華街を歩けば
10分と経たないうちにPOLICEの職務質問を受けるだろうが、
なぜか、この街には妙に溶け込んで、
道行く人は誰も関心を示さず、本人たちもそんな格好が当然のようで、
まるで違和感というものがない。
この恐れを知らぬ観光客たちは、誰もみなニコニコと楽しそうで、
彼等ナリにこの南の島を楽しんでいるのがよく分かり、
誰ひとり彼等を不審がる人はいない。
もっとも、
市役所や銀行に勤めるお堅いサラリーマンが
長髪だったりヒゲをはやしていたり、Tシャツ姿で勤務していたりする島だから、
これくらいのことは、どうでもいいか。
【高級衣料品】
この島に来てから、ずっと不思議に思っていたことがある。
日本一所得の低い沖縄県の離島で、住宅費もベラボーに高く、
※沖縄県民一人当たり平均年収204万円/全国平均271万円:平成15年統計
仕事が少なく収入を得る機会の少ない島なのに、なんとかやっている・・・
最近になってやっとその理由が分かったのだ。
この島には、JASCO系の大型スーパーやコンビニ、ファーストフード、
ビデオの「TSUTAYA」まで揃っていて、
普通の生活をするには何の不便もないのだが、
高級衣料品や高級ブランド品なんかを売っている店がないのだ。
人間の欲望は限りなく、目の前に高いけど欲しい物を売っている店があれば、
分不相応な借金をしてでも買ってしまうが、
売ってなければ欲しくなりようがないのだ。
なんて単純なことだろう。
結局のところ、高級衣料品や高級ブランド品などという商品は、
この世に存在しなくても誰も困らないものだということが、
この島に住んではじめて分かった。
内地に居るときはスーツ代だけでも年間15万円以上かかったのに、
この島では衣服代は年間2万円もかからない。
亜熱帯の島なので、皮のコートとか防寒服とかもほとんどいらない。
「衣」に金がかからないということは実は大変なことで、
この島には「エルメス」とか「バーバリー」の専門店とかは、
100年経っても進出してこないだろうと思う。
| 女性の衣服代も内地の1/10で平気だったりするようだ |
【夏と冬】
八重山は亜熱帯に属する地方で、春や秋の「めりはり」が薄い。
この島に来た最初の頃には、
まるで年中夏で、急に冬が来るおかしなところだと思っていたが、
5年も住んでみると、微妙な春・秋の季節の移り目が分かるようになった。
秋の訪れとともに吹いてくる新北風(ミーニシ)やサシバの渡りなど、
秋を感じさせる四季の“めりはり”が分かりだしたが、
その分、こちらの身体も島に慣れてきて・・・
たった12度の真冬の気温がとても寒いのだ。(八重山の最低気温は12度)
去年の冬には、この島に来てから使ったことのなかったコタツや、革ジャンパー、
電気毛布まで引っ張り出してしまった。
最初の頃は、島人(しまんちゅ)が冬になると寒そうに、
ダウンジャケットを着こんで震えているのを見て、
「馬っ鹿じゃなかろか」と思っていたが、
とうとう僕まで馬鹿の仲間入りを果たしてしまったのです。
最初の年には、年中半袖で平気で、島人(しまんちゅ)から逆に馬鹿にされたが・・・
これでとうとう、僕も立派に島人(しまんちゅ)の仲間入りを果たせたわけで、
とてもうれしいのだ。
11月頃になると、島人(しまんちゅ)ーは寒そうに長袖の上着を着こみ、
若いキャンパーたちや、観光客は半袖に半ズボンといういでたちだ。
まったく、こんな摩訶不思議な風景はこの島だけだと思う。
【ネクタイをしない】
島ではネクタイをした人をあまり見かけない。
内地の癖で、たまにネクタイをして人に会うと、
ものすごく警戒して接されているのがよく分かる。
島の人は、どうもネクタイをしている人は、内地の悪徳業者?だと思うようで、
いっぺんに警戒されてしまう。
バブル真っ只中の頃、本土や那覇から、スーツにネクタイをして、
アタッシュケースなんかを持って標準語を操る洒落た一団が島にやってきて、
いんちきマルチ商法の高額商品を売りつけたり、ローン付の高額化粧品を買わされたり、
そんな苦い経験が島人(しまんちゅ)ーにはあるらしい。
人口わずか48,000人の島でマルチ商法が成り立つはずがないのだが・・
5×5×5×5×5×5×5=78,125人、5人づつ子を増やせば、
7代目で既に島の人口を超えてしまう この島でマルチは不可能なのだ |
何かベラボーに高い羽ブトンなんかを売りつけられるのではないか、
自分の土地を二束三文で買い叩かれるのではないか・・・・
そんな警戒感がひしひしと伝わってくるのだ。
そういうわけで、今では仕事で人と会うときには、
作業着に毛が生えたようなシャツを着て、
1本1,980円でスーパーで買った綿ズボンなどをはくことが多い。
【Tシャツ文化とコピー商品】
この島には「Tシャツ文化」という衣料文化がある。
Tシャツは汗を吸いやすく、洗濯も楽なので、
高温多湿の島の生活にはピッタリなのだ。
子供からオジイ・オバアまで、Tシャツは島の暮らしには欠かせない。
「海人」というブランドのTシャツメーカーが島にはあって、
この島唯一のブランド衣料品なのだが、ロゴマークの少し違った類似海人Tシャツや、
これらの意匠を真似た畑人(はるさー)Tシャツなんかも出回ってこの市場は競争が激しい。
この海人Tシャツの偽物は、沖縄じゅういたるところに溢れている。
Tシャツ文化の話とは外れるが、
この島の人まねのスゴサには呆れることがある。
「石垣島ラー油」という人気商品があり、爆発的に売れているが、
いつの間にか「石垣島のラー油」というコピー商品が市場に出回っているのだ。


石垣島ラー油の本物 海人Tシャツの本物
こういうことは絶対いけません!人まねがオリジナルを超えることはあり得ません。
【へんし〜ん(変身)】
何度も触れたが、
この南の島では1年の大半を、半袖や軽装で過ごせるのだ。
普段着はTシャツ、仕事着は「かりゆしウェア」や作業着&野良着。
このように相場が決まっていて、高温多湿の島の生活にはこれで充分事足りる。
だが・・・・・、
八重山人が、ある時間帯になると変身することはあまり知られていない。
それは、お酒を飲みに行くときだ。
普通、内地の感覚から言えば、飲みに行くのは仕事の帰り道で仕事着のままである。
女性は多少着替えるだろうが、いわゆる「通勤着」に着替えるのだ。
基本的には、会社の同僚、上司、部下や仕事帰りの友人などと飲みに行くわけなので、
とりたてて「変身」する必要は何もないのだ。
でも、この感覚はこの島では通用しない。
島人は飲みに行くとき、仕事場から一度、家に帰りたがる。
ご飯を食べて、シャワーを浴びて、普段は見たこともない「一張羅」に身を包み、
ウルトラマンのように「変身」してサッソーと夜の街に出かけるのだ。
時刻は午後9:30を過ぎた頃の話。
実はこの島のスナックは、そのころにようやく開店する店が多いのでちょうど良いのだ。

美崎町に夜の帳が降りる頃・・・
この傾向は、何も一部の島人に限ったものでもない。
会社の忘年会やら新年会の季節ともなれば、
参加者のほとんどが一度は家に帰って、「変身」するのだ。
普段は絶対に着ないロングコートやブレザーを着込み、ネクタイまでしている者や、
冬には、女の子はふわふわの毛皮のコートやヒールの高いブーツまで履いてくる。
12月、1月の夜と言っても、気温は16〜17℃はある暖かい日が多いので、
これは、さながら仮装行列のようである。
この島では夜の10時位に「飲みに行こう!」と誘いの電話がよくある。
こんなとき、決まって僕は「軽装」で行くことにしている。
スナックに着くとやはり「変身」した2〜3人の友人が待っているのだが、
「軽装」の方が逆によく目立って、店の女の子にはウケが良いのだ。
娯楽の少ない島だからこそ、
お酒を飲みに行くことさえひとつのイベントなのだ。
昼間の仕事より真剣に取り組んでいるその姿には心から拍手を送りたい。
でも、変身する人はみな、ウルトラマンさながら、そのうち電池が切れるのが常で、
明け方に「一張羅」に身を包んだ電池切れのウルトラマンたちが、戦いを終えて、
路上でぐっすり寝入っている姿をよく見かける。
【帽子とサングラス】
この島での生活に不可欠な物は
さしあたるところ、「無い」と思っていたのですが・・・
実は欠かせないものがあった。
この島を初めて訪れた観光客が、空港でタクシーを拾って乗り込むと・・・
「お客さん、どちらから?」
などとチョイっと振り返ったタクシーの運ちゃんの顔を見て、
少なからず違和感を覚える人が多い。
運ちゃんはたいてい真っ黒いレイバンのサングラスなんかをかけているのだ。
実は
「彼には特別な任務があり、視線や心理状態を悟られないように用心している」
という訳ではまったくなく、
ただ単に眩しいだけなのだ。
真夏でも気温は33℃位までしか上がらないが、
北回帰線付近に位置するこの島の日差しはとてもきつい。
あるデータによれば、紫外線の量は関東地方の約5倍ということだ。
だから、
タクシーやバスの運ちゃんに限らず、
みんな当たり前のようにサングラスをかけている。
もう一つ
この島のきつい日差しを浴びていると、
外出時には、自然と帽子をかぶる習慣が身につく。

島の伝統的かつ代表的な帽子は「クバ笠」だ。
クバ(ビロー樹)の葉で編まれた軽くて、丈夫で、通気性もいい優れものだ。
僕も釣りに行く時などにコイツを愛用しているが、
なかなか島人のようにカッコ良くはかぶりこなせない。
サングラスをかけて、クバ笠をかぶり自転車でさっそうと走るオジィの姿を
この島では良く見かける。
【五(いつ)の四(世)までも】
八重山には「みんさー織」という織物がある。
発祥地は竹富島とされているが、今日でも八重山では盛んに織られている。
漢字では「綿狭(めんさ)」と書き、要するに昔は綿の幅の狭いものを織っていた。
男性の着物の帯もその一つだ。
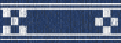
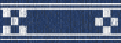
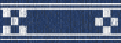
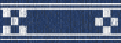
「みんさー織」には
サイコロの目の「五」と「四」のような特徴的な模様が施されていて
これは「五(いつ)の四(世)までも末永く」という意味が込められている。
勘のいい方はお気づきでしょうが・・・
男性のプロポーズに対する女性からの「返事」の証だったのです。
今でこそTシャツなどが普段着なのだが、
かつては、通気性の良い、麻や糸芭蕉で織った着物を普段着として着用しており、
女性が思いを込めて織った帯を、男性が肌身離さず使い続けたのです。
うーん、なんてロマンチックなんだろう。
話は現代に戻って・・・
僕の手元にある資料が置かれている。
それによると、
1985年以降、この島は、日本一の「離婚率」のタイトルを連続して
防衛しているらしい。
これについては、
「島人が正直者で表裏のない心の持ち主だから」と、
僕は好意的に解釈しているのです。
この島の素朴な島人は、誰かさんとは違って、二股かけた恋愛ができないのだ。
何度でも「五(いつ)の四(世)までも末永く」
| ボクシングの世界タイトル防衛記録の具志堅用高もこの島の生まれだ |
【島ぞうり(島サバ)】
島草履(しまぞうり)とは、沖縄の鼻緒付きのスリッパだ。
八重山では「島サバ」と呼ばれる。
島サバは、そのままビーチに行くこともできるため、とても人気が高い。
八重山人(やいまんちゅ)にとって一番接することの多い履き物で、
子供のころから島ぞうりを愛用しつづける人も多く、
靴や靴下もあまり履かない。
いつでも島サバを履いているため、
足の甲に鼻緒型(V字型)に白く染め抜いた日焼けが残るのだ。
日焼けと言えば、内地には、
「ゴルフ焼け」とか「外車焼け」とかいうステ−タス焼けがあるが、
もちろん「ぞうり焼け」というステ−タス焼けはない。
この草履のことを、
「便所草履」と悪口を言う人がいくら居ても、
この八重山の「ぞうり焼け」は、
八重山人の誇りであって、けっして貧乏臭い日焼けではないのだ。


しかし、ただのゴム草履もここまでくると、
それはそれで、とても立派なものだと思う。
| あまりの人気度の高さから、これは一種の沖縄文化と言っていいのだ |
【ルーズソックス】
1990年頃から流行し一世を風靡した中高生のルーズソックス。
今や、「かわいい」というより「流行遅れ」の代名詞のように扱われ、
ルーズソックスの火付け役の会社も、とっくに倒産したらしいが、
この八重山では、今もどうして、健在なのだ。

ルーズソックスを履くことによって、にわかに自分を主張し始めた女子中高校生たちは、
この人目を引くファッションと、
大人顔負けの化粧によって、初めてマトモに大人たちの視線を集めることに成功した。
ルーズソックスに目を留めることよって、大人たちは、
「大人予備軍」である女子中高校生たちの存在に、初めて気づくことになったのだ。
慣れない化粧の下の素顔の女子中高校生たちは、どんな欲望や希望を持ち、
何を考え、何を主張しようとしているのか・・・・
今や、アダルトビデオの世界でしかお目にかかることのない
内地では絶滅に近いルーズソックスを履いた大人びた八重山の子供たちの多くは、
高校を卒業すれば、職のないこの島を捨てて、
憧れの那覇や内地の都会に、たったひとりで出て行く。
そこではきっと、
慣れ親しんだのんびりした八重山の生活スタイルでは通用しない過酷な競争社会や、
大人たちの社会ルールに翻弄(ほんろう)される「ひとりきり」の生活が待っているのだ。
この島で、一足早く大人の練習をするのもいいことかもしれないね。
ちばりよー(頑張れよ) 八重山の子供たち。
高校新卒者の就職率は、沖縄が全国最下位なのだ。
※県内に職がない |
【八重山上布】
八重山上布(じょうふ)という伝統的な手織物がある。
八重山上布の材料は、苧麻(ちょま)の繊維で、
苧麻で織った布は「苧布(おぬの)」と呼ばれ、八重山方言では「ブーヌヌ」と言うのだ
 苧麻
苧麻
苧麻は、イラクサ科に属する多年生の植物で、
東南アジアが原産地で、現在の主産地は中国・マレーシア・フィリピンなどだ。
越後上布、小千谷(おじや)縮、能登上布、近江上布、奈良晒布、宮古上布なんかも、
八重山上布と同じく、この苧麻が原料だ。
苧麻は、天然繊維の中で最も爽やかな清涼感があり、腰があって軽く、
吸収性や通気性に優れた沖縄向きの繊維だ。


この八重山上布は、
薩摩藩による琉球支配が持ちこんだ人頭税と密接に関係がある。
琉球王朝時代の人頭税は、
男は穀物、女は上布での貢納が義務づけられ、
八重山の女たちは、伝統的に手織り上布を織った。
厳しい貢納布制度が実施されたおかげで、
八重山人(やいまんちゅ)は、王府の指揮と監督下で織物に従事する事となり、
その結果、紡績技術が飛躍的に向上し、
精緻な織り柄がどんどん織り出されていったのだ。



上布(じょうふ)というのは「上等の布」という意味で、
出来の悪いものは「中布(ちゅうふ)」と呼ばれるが、
昔は「下布(かふ)」と呼ばれるもっと出来の悪い布もあったそうな。
八重山上布はとても味がある布なので、涼しげな暖簾(のれん)が欲しいのだが、
すべて手織りだけあって、僕には高すぎて手が出ない。
ちょっと出来の悪い下布(かふ)の暖簾でもいいから、
どこかで探してきて、玄関に掛けたいと思う。
沖縄の夏には涼しげな布が一番似合う
今では、この苧麻の績手(うみて)は島でただ一人、
この道70年になる85歳の「豊川ふみ」さんだけになり、この人が亡くなれば大変なことになるらしい。 |

 の話
の話
 の話
の話








 苧麻
苧麻



