浜下り(はまおり)とビーチパーティ <海は八重山人の故郷>
このページは、毎月1回、その月の八重山を紹介していく歳時記のページです。
不思議の国、八重山の歳時記は内地のそれとはちょっと違うのです。
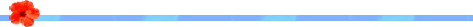
【4月の八重山歳時記】
八重山の4月行事のNo1は、浜下り(はまおり)です。
浜下り(はまおり)とは潮干狩の行事のこと、八重山ではこれを「サニズ」または「サンガジャー」とも呼び、いずれも三日(みっか)の意味だ。八重山では「三日」のことを「みっか」とは言わず、「さんにち」と言うので「サニズ」となる。当然、五日は「いつか」ではなく「ごにち」、「十日」は「とうか」ではなく「とっか」だ。
何故そうなるのかは?・・・・・分かりません。
沖縄では、旧暦三月三日(上巳の節句:雛祭り)に浜に下りて潮干狩りをして遊ぶ。
元来、この行事は旧暦3月3日の大潮時に女性が海水で身を清める儀礼的目的の“禊ぎ”から始まったとされ、本来は内地の雛祭り同様、女性たちの行事だが、今では八重山人が家族そろって浜に出て潮干狩りに勤しむという海遊びのレジャーの日となった。
 こんなごちそうを作って重箱や折りに詰め、干潮に合わせて浜に着くように家を出る。シャコ貝やタカセガイ、タコ、ウニ、サザエなどを獲る。タイドプールで逃げおくれた魚も獲れるのだ。 こんなごちそうを作って重箱や折りに詰め、干潮に合わせて浜に着くように家を出る。シャコ貝やタカセガイ、タコ、ウニ、サザエなどを獲る。タイドプールで逃げおくれた魚も獲れるのだ。
八重山人は、とにもかくにもお祭り好き、本来の“禊ぎ”の意味なんかはとっくに忘れ、これは要するに沖縄特有の「ビーチパーティ」なのだ。
八重山は年中暖かいので、春になって花(桜)が咲き、花に浮かれて花見するというような習慣はない。浜下りは内地の花見に代わる春:初夏の訪れを祝うお祭りだ。
海の近くに住む人たちは海を中心によく遊ぶ。
一年中、海で魚を獲っている漁師でさえ、イカ釣りのシーズンになると、夜な夜なイカを釣りに行く。たった5匹しか釣れないイカだから、けっして「仕事」で海に出るのではなく「遊び」で海に出るのだ。これは沖縄の海人(うみんちゅ)も内地の漁師も変わらない。
海は、彼らの職場であるとともに遊び場であり、職業漁師でなくとも海の近くに住む人たち共通の故郷なのだ。海というものは、それだけの魅力に満ちているということで、八重山人(やいまんちゅ)がよく言うことのひとつに「貧乏しても海に行けば生きていける」という言葉がある。何人もの八重山人からこの言葉を聞いた。
この清廉な八重山の海の向こうには、北に行けば日本(やまと)があり、南に行けばフィリピンやインドネシアが、西には台湾・中国がある。アジアの入口八重山に住む人たちは、何処に行くにも海を渡って行く、海は八重山人共通の“こころの故郷”なのだ。
3月3日に海や山に遊びに出る風習は、もともと雛を送ったり祓に水辺に出たりした行事の変化したものだ。雛壇の前でする遊びを「磯遊び」というところもあり、九州西側の沿海地方では雛祭の日に海岸に出て遊び、山口県の周防大島などでも同じ日に磯遊びをする。周防大島では「磯祭」と称して乙女たちが浜で草餅を食べる風習がある。
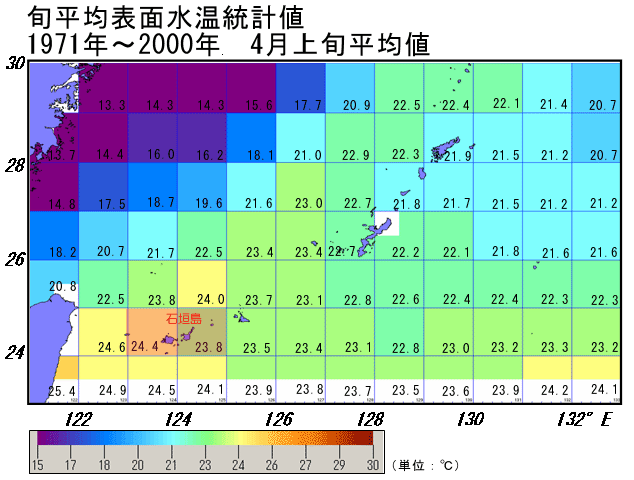
この頃になると、八重山の海水温は23〜24℃まで温み、太陽は輝きを増して浜は青一色、こんな綺麗な海になるのです。

| この浜下りの習慣は、別に沖縄−八重山だけでなく鹿児島や宮崎など南の県を中心に広く見られ、南の島では女の人はこれをしないと、蛇の子を身ごもるとされたのだそうだ。 |

この写真は、石垣市街地から5分で行ける浜での写真だが、こんな市街地近くの波静かな内海のタイドプールにも、色鮮やかなコバルトスズメやブダイ類が群れ泳ぎ、さんさんと輝く沖縄の太陽は早くも夏の装いを感じさせる。
八重山でシュノーケルをして遊ぶにはこんなタイドプールの中が一番だ。
内地から越して来た人たちは水着でシュノーケル遊びに興じるが、かなり現実的な性格の八重山人はほとんど海には入らず、もっぱら磯でアーサー(アオサ)やスーナ、モズクなどの海藻採りやシャコ貝やタカセガイ獲りなど、晩御飯のオカズ探しに忙しい。
  
※これがスーナ 歯ごたえが良くてなかなかイケル シャコ貝 タカセガイ
今夜の夕食は海鮮料理だぜ!
 4月になると、あのホタルの出番。 4月になると、あのホタルの出番。
八重山最大のネイチャーイベント、清楚なヤエヤマヒメボタルの光は、華麗と幻想の自然のナイトショーだ。
※世界中で八重山しか生息しないこのホタルの地表スレスレに飛ぶ清楚な輝きと圧倒的な数の群翔は、まるで光の絨毯のよう、3月下旬〜6月上旬の期間限定イベント この季節の八重山の旅でホテルでじっとしていることはありません
ヤエヤマヒメボタルの華麗な飛翔は、光の渦を振りまきながら飛ぶディズニーのティンカーベル(TinkerBell)の世界そのもの、あなたも八重山の夜のお伽の国を覗いてみませんか? |
不思議の国八重山の4月のお話です。
|