2月の田植えと「十六日祭」 <あすの新聞休みです>
このページは、毎月1回、その月の八重山を紹介していく歳時記のページです。
不思議の国、八重山の歳時記は内地のそれとはちょっと違うのです。
【2月の八重山歳時記】
この季節になると、地元日刊紙「八重山毎日新聞」には、決まって面白い記事が載る。
その記事は、
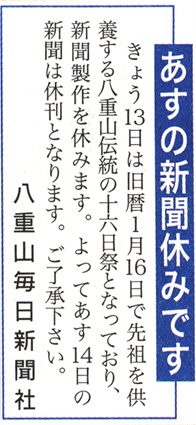
八重山毎日新聞誌より
|
天下の日刊新聞社までもが休むほど重要な「八重山伝統の十六日祭」というのは何かというと、
八重山では旧暦1月16日は「後生の正月(ぐしょうの正月)」とも呼ばれる十六日祭(ジュウルクニチー)で、先祖供養の行事として旧盆と並び、八重山地方では過去も現在でも、もっとも重要な島の伝統行事のひとつなのだ。
日本(やまと)でも、旧暦1月16日は、古くは「地獄の釜も開く薮入り」と呼ばれ、いろんな行事で正月同様に賑わったが、日本では、もうそんな風習もとっくに廃れて短くはないのだが・・・
|
「地獄の釜も開く薮入り」
日本でも旧暦の1月16日は、7月16日と並ぶ「薮入り」だ。
もともと「薮入り」という言葉は、奉公人が盆・正月に国許、親元に帰ることを言うのだが、明治の中頃までは、「丁稚(でっち)」と呼ばれた見習い期間中の奉公人は最初の三年間は薮入り休みを
もらえなかったそうだ。もともと、「丁稚」は十歳にも満たないあどけない子供のことだから、辛 い丁稚奉公から解放され親元へ帰って、里心が付いたらいけないという配慮からだった。
でも、こんな1月16日の薮入りの風習も内地では、ほとんど廃れてしまったが、ここ不思議の国八重山では、形を変えながらも「十六日祭」として今も脈々と息づいているのです。
琉球王朝時代、正月1日〜15日までは城内の諸行事を済ませて、16日には臣下を父母への年頭のあいさつのために帰郷させたというが、ある臣下が家へ帰ってみると、父母は既に亡くなっていてこの世のものではなかったので、墓参りをして年頭の辞を墓前で述べたのがその始まりだとも伝わる。 |
「十六日祭」には、沖縄本島に働きに出ている人や、内地に出ている親族たちも職場の休みをもらって島に帰ってくる。
親族・血縁が先祖の墓の前に集まって、ゴザを広げて花を生け、重箱料理、お菓子、果物や酒などを供えて線香を焚き、持ち寄った料理を食べながら一騒ぎして過ごす。もちろん三線も出番です。これが八重山独特の供養祭「十六日祭」だ。
十六日祭の前には、墓参りのために家族総出で墓掃除をする。墓地では家族連れがカマや竹ほうきを手に草刈りをしたり、墓の周辺の枯れ木の伐採、掃除をする姿があちこちで見られるのだ。
  
墓地と言えば、沖縄の墓は「亀甲墓(かめこうばか)」と呼ばれ「子宮」の形をしているそうで、人間が死んだ後は生まれてきた母親の「胎内」に戻っていく、という意味で背が高く丸く大きいのだと言われるが、実際には、火葬しない遺体を収めた棺桶をそのまま墓室に入れるという土葬形式なので、人が出入りしやすいよう、大きく背の高い墓室が必要という実用上の造りなのだ。

石垣島以外の離島には、今でも仏教寺院や教会はなく(竹富島には「喜宝院(きほういん)」という浄土宗本願寺派の小さな分寺があるが、2坪ほどの内陣(ないじん)があるだけで「仏教寺院」と呼ぶには寂しい)当然、竹富島以外の離島には僧侶や神父などは居らず、葬儀屋もないので、仏が出ると地域の住民が集まって手作りの葬儀葬礼をする。
また、火葬場は石垣島にしかなく、離島には火葬場がないので、今も「土葬」で、これも沖縄の伝統文化の一環なのだ。
土葬文化の沖縄には土葬禁止条例がなく、火葬場がない離島地域の人たちは、もっぱら土葬が慣行だ。 |
この十六日祭の習慣は、単なる祖先供養の行事というよりも、親戚一同が集まって死者をも抱きこみながら繰り広げる壮大な同族コミュニケーションと言えるものだ。これはもう沖縄が誇るひとつの文化大イベントなので、おまわりさんだって、もちろん新聞屋さんだって、お休みです。
(ホントは、当然、警察は開いてます。でも、この日に休暇を取る警察官は多い)
そんな祭に子供のころから親しんでいる八重山の子供たちは、「墓場」を怖いものとは思っていない。
十六日祭で家族と遊んだり、前庭で弁当を広げたりして、みんな子供の頃から慣れ親しんでいる思い出深い楽しい場所なので、墓場=怖いという考えは、日本(内地)のもので、八重山の少年少女にとっては、ここは、人の来ない安心できるデートの場所だったりもする。
そう言えば、沖縄映画の名作「ナビーの恋」のデートの場所も墓場だった。
 |
映画「ナビーの恋」から |
こんな十六日祭に必ず登場する沖縄の「重箱料理」というのは、
もともとは、中国風の羊・牛・豚(三牲)それぞれ一体を供える本格的な三味料理だったそうで、現代の沖縄の「重箱料理」は、それを簡素化したものだと言われている。
 |
|
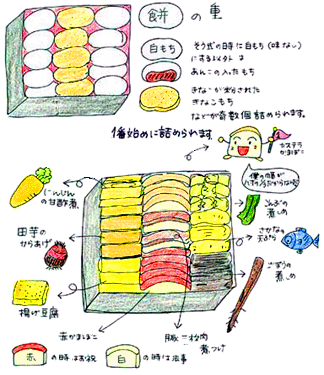 |
「重箱料理」はこういうやつで、揚豆腐・魚天ぷら・かまぼこ・三枚肉の煮付け・ごぼうの煮付け・こんぶ・こんにゃくなどが入ったこんな感じ、別の重箱には、おもちを入れて、2段重にする。
何度か「おすそ分け」を貰って食べたけど、これはなかなかイケル。
沖縄料理というものは、歴史的、また地理的な特徴を象徴するように、中国、東南アジア、そして日本の影響を受け育ってきたもので、かつての琉球王国で中国皇帝から派遣される「冊封使(さっぽうし)」の接待をする目的で発達し、その後に琉球王国が無くなれば、この料理は沖縄の家庭料理へと進化しながら、庶民の暮らしの中に少しづつ浸透していくようになったのだ。
現在の沖縄料理にもうひとつ強い影響を与えたものが、太平洋戦争後24年間続いたアメリカ統治下における、まさにアメリカのファーストフーズ食文化なのだ。
戦後、アメリカ本国から続々と沖縄に送られてきた大量の物資や食材は、沖縄のこれまでの食習慣を大きく変えることとなって、つまり、現在の沖縄人の食べている沖縄料理は、琉球宮廷料理の伝統とアメリカ的洋風料理の実にうまく溶け込んだ結果と言える。
話を元に戻すと、先祖の前で賑やかに過ごし、親族の無事を願ったり、親族同士の近況報告も兼ねたりという、とても明るいお墓参りが十六日祭で、この墓参りらしくない墓参りは、とても八重山的で素晴らしい民族習慣だと思う。
不思議の国八重山の2月には、もっと不思議な光景も見られるのだ。
この写真は「田植え」、亜熱帯の島八重山ではなんと・・・1月末から2月初旬に田植えが始まる。

亜熱帯性海洋気候の八重山では、未だに一部の農民は米の三期作(辞書にも二期作という言葉の登録はあるけど三期作はない。年に3回、同じ作物を植えること。)をする。
第1回目の田植えは1月末〜2月、もちろんこれは日本一早い田植えで、まだまだ雪に閉ざされた東北のお百姓が見たら腰を抜かす出来事だろう。
石垣市の水田地帯では1月末から早くも今年の1期米の田植えが始まった。初植えの品種はコシヒカリ、この日本一早い田植えの稲は、5月15日ころから収穫すると言う。
ベトナムや中国の一部、台湾などでは三期作も一般的だが、日本国内で三期作が行われているのは八重山だけなのだ。
※水稲は気温12℃以上で発芽する 八重山では真冬でも12℃以上の気温なので、季節を問わず種を蒔けばいつでも苗が出来る
それで、というわけではないが、このお百姓さんが被っている帽子「クバ笠」、クバと呼ぶビロウ樹(蒲葵、枇榔、檳榔)の葉で編まれた笠は、どことなくベトナムの笠「ノンラー」にとても似ているではないか!
 |
 |
 |
 |
| 八重山のピロー樹(クバ) |
クバ笠 |
八重山のクバ笠 |
ベトナムのノンラー笠 |
八重山では、この笠は、ベトナムの「ノンラー」同様に、今もどうして、しっかりと実用品で、けっして日本(やまと)の蓑笠のように観光土産品に落ちぶれてはいない。多分、このクバ笠は、あと50年経っても八重山では現役を続けているでしょう。これが「文化」というものです。
十六日祭が終わると・・・・・・八重山にもそろそろディゴの花咲く春がやってくる。
今月の島のイベント
12日(土) やまねこマラソン
場所:西表島西部
種目:23キロ/10キロ/3キロ
16日(水) 十六日祭(旧暦1月16日)
27日(日) 黒島牛まつり
場所:黒島多目的広場
不思議の国八重山の2月のお話です。
|